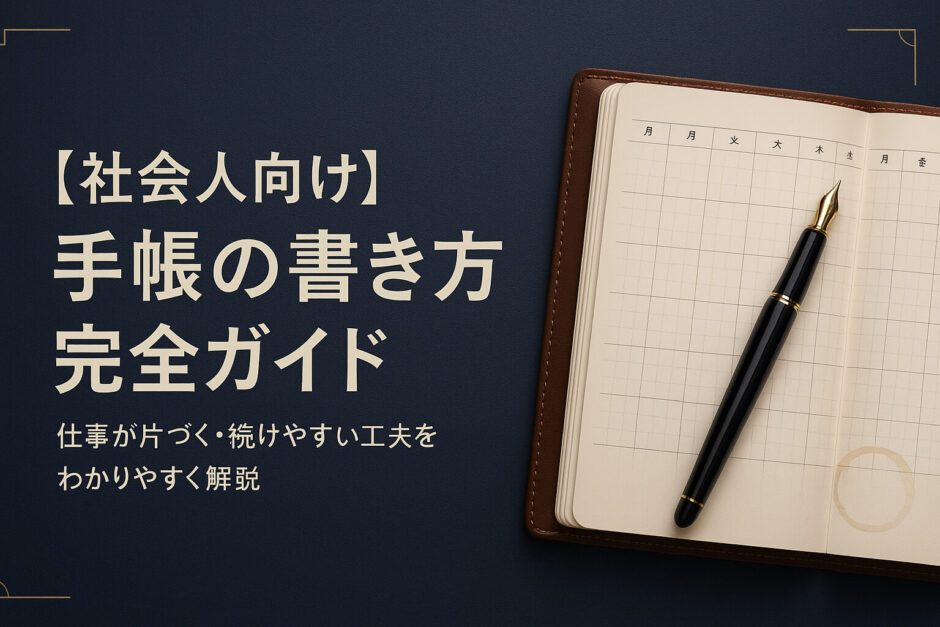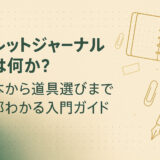社会人になると、予定管理・タスク管理・メモなど扱う情報が一気に増え、「手帳をうまく使いこなせない」と悩む人は少なくありません。ですが、手帳は書き方のコツさえ掴めば、仕事の抜け漏れが減り、段取り力が上がり、毎日のストレスが大きく軽減されます。本記事では、今日から誰でも実践できる“社会人のための手帳の書き方”を、目的別にわかりやすく解説します。
目次
社会人が「手帳の書き方」でつまずきやすいポイント
仕事で手帳を書こうとしても、三日坊主になったり、使い方が定まらなかったりと悩みが出やすいものです。よくある原因は以下の3つです。
続かない・書き方のルールが曖昧
最初から完璧なフォーマットを求めると挫折しがちです。「最低限書く項目を3つだけ決める」など、ゆるめのルールが継続しやすさにつながります。
仕事とプライベートが混ざって書きにくい
ページがごちゃつくと管理が難しくなります。対策は、役割ごと(仕事・私生活)に色分けするか、ページを分ける方法が効果的です。
手帳を使う“目的”が曖昧
予定管理なのか、タスク整理なのか、アイデアメモなのか…。目的がはっきりすると手帳の選び方や書き方が自然と定まります。
社会人に最適な手帳の選び方
書き方よりも、まず「どのフォーマットを選ぶか」が大きく影響します。
ウィークリー・デイリー・マンスリーの違い
- マンスリー:予定の俯瞰向け。シンプルで最も続けやすい。
- ウィークリー:予定とタスクの管理に最適。社会人の定番。
- デイリー:1日を細かく記録したい人向け。メモ多めの職種と相性◎。
サイズ・フォーマットの選択基準
- A5:書き込み量が多い人に最適。デスクワーク向け。
- B6:携帯性と書きやすさのバランスが良い。
- ポケットサイズ:外回りが多い仕事で便利。
仕事スタイル別の選び方
- 会議が多い職種:ウィークリー+メモ多め。
- 外出が多い:薄型マンスリー。
- クリエイティブ系:自由度の高いデイリー。
【比較表】手帳フォーマットの特徴まとめ
| フォーマット | 向いている人 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| マンスリー | 予定管理中心 | 俯瞰しやすい/軽くて持ち運びやすい | メモ欄が少なめ |
| ウィークリー | 予定+タスク管理 | バランスが良く社会人の定番 | ページ数が多く厚くなりやすい |
| デイリー | メモが多い職種 | 自由度が高く思考整理に最適 | 毎日書かないと空白が目立つ |
社会人のための手帳の書き方【基本編】
① 毎日の「固定予定」を最優先で書く
会議・来客・締め切りなど動かない予定を最初に記入します。これにより「空き時間」が見えるため、タスクの配置がスムーズになります。
② タスクは“時間”とセットで書く
ただのToDoリストではなく、以下のように作業時間とセットで書くことで実行率が上がります。
- 10:00〜:企画書案出し(30分)
③ メモ欄は“思考整理スペース”として使う
会議の気づき・アイデア・進捗など、自由に書けるスペースを1日1つ確保すると思考の整理がしやすくなります。
仕事が早くなる手帳術【実践テクニック】
優先順位のつけ方(ABC法・3MIT)
- A:必須のタスク(今日必ずやる)
- B:できればやるタスク
- C:余裕があればやるタスク
さらに、1日の「最重要タスク3つ(3MIT)」を先に決めておくと、迷いなく行動できます。
プロジェクトページを作る
手帳の後ろに案件ごとのページを作り、タスク一覧・期限・進捗をまとめておくと全体像が一瞬で把握できます。
週次・月次レビューのやり方
週次レビュー:今週できたこと/来週の優先順位を3分で整理。
月次レビュー:達成・改善点を振り返り、翌月の計画に反映します。
今日から実践できる「続けるコツ」
フォーマットを決めすぎない
綺麗に書く必要はありません。むしろ汚くてOKくらいの方が続きます。
毎日5分の書き足しルーティン
朝か仕事終わりに5分だけ手帳を開く習慣をつくるだけで十分です。
内容を3項目だけに絞る
- 予定
- 今日のタスク3つ
- メモ1つ
これだけでも仕事の抜け漏れは大幅に防げます。
手帳と相性のいい便利アイテム・アプリ
色分けに便利なペン
仕事・私生活・重要事項などを3〜4色で分類すると視認性がアップします。
スマホと併用するシンプルルール
- 予定:スマホで管理
- タスク/メモ:手帳
役割分担を決めることで、手帳が続きやすくなります。
まとめ|自分に合った書き方を見つけよう
手帳は「完璧に書く道具」ではなく、仕事をスムーズにするためのサポートツールです。まずは今回紹介した基本と続けるコツを試し、自分にとって最適な使い方を見つけてみてください。